山陽リレーコラム「平井の丘から」
アナログ時計の時空に想うこと 江口 瞳[2019年9月30日]
多様な現代において、デジタル時計とアナログ時計のどちらを好むかといった問いは愚問かもしれない。このような中で、あえて、アナログ時計で味わう感覚について述べたい。
以前に、それまで使用していたアナログ時計からデジタル時計に換えたことがある。しばらくして、デジタル時計が示す文字に刻々と追いかけられ、不思議な緊迫感を受け、そのうち、電池が切れてからは使用しなくなっていた。アナログ時計では、昼食時までにあと何分ある、今日の昼食は何にしようかと思いを巡らす、あれはいつだったかと過去にさかのぼる、時空の広がりさえある、アナログ時計ならではの感覚に思える。
看護師は、患者の脈を測るのは日常的なことであり、アナログ時計が好ましい。アナログ時計により、患者の脈を数え、同時に脈拍のリズムや強弱、あるいは患者のその時の状態を観察し、何をすべきかを考えている、専門的な職業の世界がある。
アナログ時計とデジタル時計をうまく使い分けている人も多いかも知れない。どちらかの時計の是非論でもない。
豊かで、便利なこのデジタルな生活空間の中で、アナログ時計の世界に繰り広げられる感覚、時をふと止め、瞬間に想いを巡らす、この感覚を大切にしたい。
姑からもらった、今は引き出しの中にある電池切れしたデジタル時計が、私のアナログ時計の世界で、大切に動いている。アナログ時計の中での感覚の広がりや奥深さを、心に余裕を持って刻みたいものである。
令和元年(2019年)9月吉日
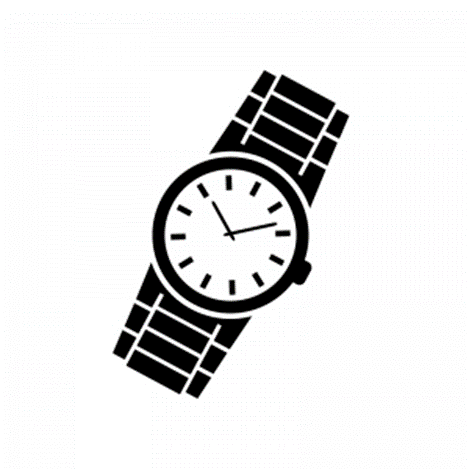
生業をつくり直す 建井 順子[2019年9月10日]
私はこれまで生業を生み出す人々に焦点を当て、事業がどのように成長してきたのかを調査してきました。それらは、一般的にはほとんど知られていない、地方の企業経営者や事業代表者がほとんどです。しかし、そうした人々の人生には、私たちを魅了し、示唆を与えるものが少なくありません。ここでは、そうした例を一つ紹介しましょう。
ご紹介するのは、福井県鯖江市出身の蒔絵師Aさんのこれまでの歩みです。蒔絵とは、漆工芸の一種で、漆で文字や絵などを描いたうえから金や銀を蒔くことによって装飾する技巧のことを言います。
蒔絵師の家系に生まれたAさんは、後継者となるべく、他の地域の蒔絵師のもとで修業を積みました。しかし、修業を終えて故郷に帰ってくると、大衆消費の拡大を背景に、伝統的な技法は軽視され、商業的な技法が好まれる時代となっていました。そうした流れに納得できなかったAさんは、百貨店の実演販売や神社の骨董市など、本来蒔絵師が出ていくことはありえなかった場に積極的に出ていきます。そこでは消費者と直接対面するため、率直であるがゆえに傷つくような意見をたくさんもらいます。反面、そうした意見がヒントとなり、従来蒔絵が使われることのなかった製品に蒔絵を使うアイディアを得て、新たなマーケットを開拓していきます。
現在、Aさんは東京に拠点を置いて蒔絵教室を運営する傍ら、海外のコーディネーターとつながることで、蒔絵の技巧を世界に広げようとしています。このようにAさんは、自分が持つ技能を核として、伝統的な生業を新たな形態のものにつくり直してきました。この例のように、第一線で活躍している経営者、事業代表者の方に共通しているのは、生業をつくり変えることを決して恐れず突き進む、強い姿勢なのです。